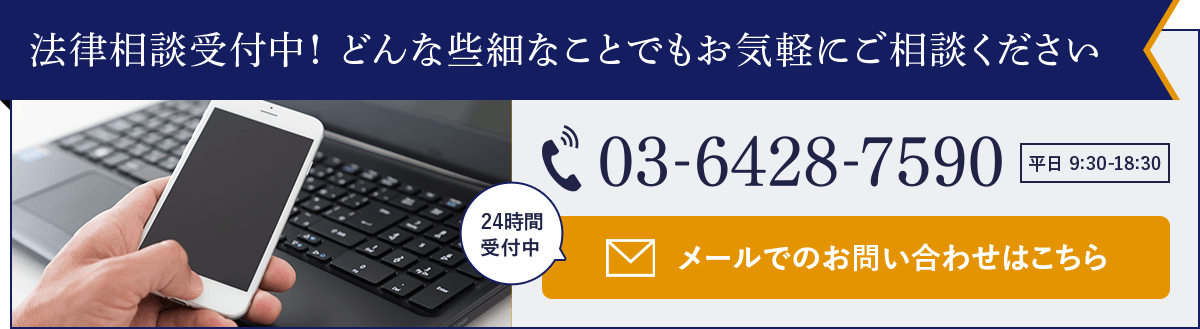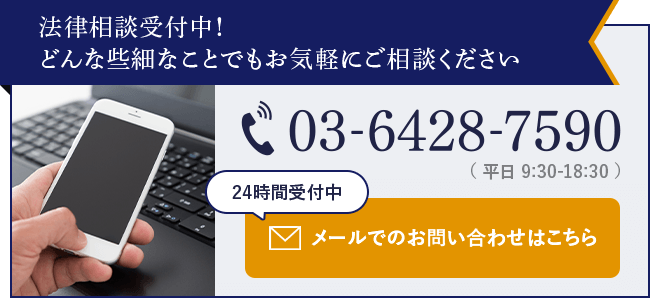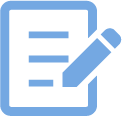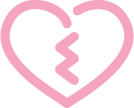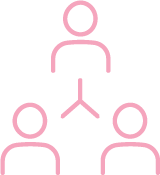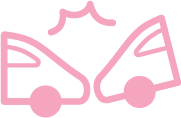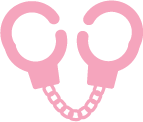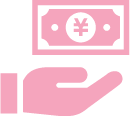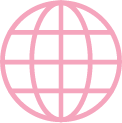育休復帰後の配置転換は違法になる?アメックス事件と会社の対応について解説
1. はじめに
総務省の「労働力調査(基本集計)」 によれば、2023年の雇用者総数に占める女性の割合は約46%に上昇しています。他方、少子高齢化社会の深刻化から、企業においては、労働者の担う家族的責任に配慮した雇用管理がますます必要とされてきています。
男女雇用機会均等法(以下、「均等法」とする。)や育児介護休業法(以下、「育介法」とする。)によれば、妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、この「不利益取扱い」の具体例として、厚生労働省令 は、「解雇すること」、「降格させること」、「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」、「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと」、「不利益な配置の変更を行うこと」などを挙げています。
参考法令
① <男女雇用機会均等法第9条第3項(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)> 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
② <育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)>事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
近時の重要判例として、育休復帰後の配置変更などが、「不利益取扱い」にあたるか否かが問題となった裁判例があります。本記事では、アメックス事件・東京高判令和5年4月27日・判タ1523号 129頁について解説します。
2. 事案の概要
⑴ 当事者
原告・控訴人Xは、Y社に平成22年から正社員として雇用され、クレジットカードを発行するY社の個人営業部において、37人の部下を擁するチームリーダー(営業管理職の部長)として営業業務に従事していた。
被告・被控訴人Y社は、クレジットカードを発行する株式会社である。
⑵ 出産前後の経緯
-
- 出産前、Xは、Y社において、37人の部下を擁するチームリーダーとして営業業務に従事していた。
- Y社は、Xが産前休業に入ると、仮のチームリーダーを選任してXチームの業務を継続していたが、Xの育児休業中に組織変更を理由としてXチームを消滅させ(本件措置1-1)、Xが復職すると、新設した部門に配置し部下のいないマネージャーとして(本件措置1-2)、新規販路の開拓に関する業務を行わせ、その後は専ら電話営業に従事させた。かかる配置は、降格等を伴うものではなく基本給等の減額はなかったが、業績連動給は減少した。
- その後の組織変更(本件措置2)において、新設した部署のチームリーダーにCを配置し、Xをチームリーダーに戻すことはなく、引き続き部下を持たないマネージャーとして同様の業務に従事させた。
- また、Y社は、Xの復職後最初の人事評価において、リーダーシップの項目の評価を最低の評価とした(本件措置3)。
⑶ 争点
本件のXは、復職後に新設したセールス部門に、チームリーダーではなくマネージャーとして配置されたが、職務等級に変更はなく、基本給及び特別営業手当は減額されることはなかったものであり、本件各措置が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 」(均等法)9条3項及び「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育介法)10条が禁止する「不利益な取扱い」に該当するか否か。
3. 裁判所の判断
本判決は、以下のとおり、判示して、Xの請求を一部認容した(以下の見出し・傍線・太字はすべて筆者による)。
⑴ 一般論
一般に、基本給や手当等の面において直ちに経済的な不利益を伴わない配置の変更であっても、業務の内容面において質が著しく低下し、将来のキャリア形成に影響を及ぼしかねないものについては、労働者に不利な影響をもたらす処遇に当たる。
均等法及び育介法の趣旨及び目的に照らせば、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業等を理由として、労働者につき、育児休業申出、育児休業等を理由として、上記のような不利益な配置の変更を行う事業主の措置は、原則として同各項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、当該労働者が当該措置により受ける有利な影響及び不利な影響の内容や程度、当該措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて当該措置を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき当該措置を執ることなく産前産後の休業から復帰させることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、当該措置につき均等法9条3項又は育介法10条の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同各規定の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
⑵ 本件措置1-1について
Xの育児休業中にXチームを消滅させた本件措置1-1は、Y社の業務上の必要に基づくものであり、Xの妊娠、出産、育児休業等を理由とするものとは認められない。
⑶ 本件措置1-2について
Y社が復職したXに一人の部下も付けなかったのは、専ら、Xに育児休業等による長期間の業務上のブランクがあったことと、出産による育児の負担という事情を考慮したものというべきであって、本件措置1-2は、Xの妊娠、出産、育児休業等を理由とするものと認めるのが相当である。
Xが復職後に就いたアカウントマネージャーは、妊娠前のチームリーダーと比較すると、その業務の内容面において質が著しく低下し、給与面でも業績連動給が大きく減少するなどの不利益があったほか、何よりも妊娠前まで実績を積み重ねてきたXのキャリア形成に配慮せず、これを損なうものであった。
Xは、短時間勤務制度は利用せず子供を保育園に預けて、妊娠前と同様にチームリーダーとして活躍し、会社の中でキャリアを高めていくことを望んでいたが、Y社とXとの間において、Xの将来のキャリア形成も踏まえた十分な話合いが行われておらず、復職前に副社長から復職後の業務について半ば一方的に説明を受けたものであり、Xは、部下が付けられないことに戸惑い、渋々ながらこれを受け入れたにとどまるのであって、Xにつき自由な意思に基づいて当該配置を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない。
妊娠前には37人の部下を統率していたXに対し、一人の部下も付けずに新規販路の開拓に関する業務を行わせ、その後間もなく優先業務として自ら電話営業をさせたことについては、業務上の必要性が高かったとはいい難く、Xが受けた不利益の内容及び程度も考え合わせると、当該措置につき均等法9条3項又は育介法10条の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するということもできない。
本件措置1-2は、復職したXに一人の部下も付けずに新規販路の開拓に関する業務を行わせ、その後間もなく専ら電話営業に従事させたという限度において、均等法9条3項及び育介法10条が禁止する「不利益な取扱い」に当たるほか、Y社の人事権を濫用するものであって、公序良俗にも反すると認めるのが相当である。
⑷ 本件措置2について
本件措置2自体は、Y社の人事権の範囲内のことであって、違法であるということはできないものの、引き続きXに部下を付けることなく電話営業等を行わせた限度において、均等法9条3項及び育介法10条が禁止する「不利益な取扱い」に当たるほか、Y社の人事権を濫用するものであって、公序良俗にも反する。
⑸ 本件措置3について
本件措置3において、リーダーシップの項目が最低評価とされたのは、復職したXに一人の部下も付けずに新規販路の開拓に関する業務を行わせ、その後間もなく専ら電話営業に従事させた結果であるといわざるを得ず、この点が均等法9条3項及び育介法10条が禁止する「不利益な取扱い」に当たる以上、本件措置3についても、これに当たるほか、Y社の人事権を濫用するものであって、公序良俗にも反すると認めるのが相当である。
4. 解説
- まず、均等法9条3項又は育介法10条の不利益な取扱いに該当するというためには、当該措置がXの妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後休業又は育児休業の取得を理由にされたものであることが必要になりますが、本判決は、出産前後の幹部職員の発言内容から、本件措置1―2などについて、これを肯定しています。
- 次に、「不利益取扱い」の該当性について、本判決は広島中央保健生協事件(最一小判平26年10月23日民集68巻8号1270頁、判タ1410号47頁)の判断枠組みが参照されています。上記最判は、「均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法93 項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解される」。また、不利益取扱いにあたったとしても、「①当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は②事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらない」と判示しています。
そして、育介法は、同法10条の規定が強行規定と解すべきことなどは、均等法9条3項について述べるところ同じであると解されている(上記最判の補足意見参照)ため、育介法10条の「不利益取扱い」についても、同じ判断枠組みを用いることができると考えられます。
- 本件のXは、復職後に新設したセールス部門にマネージャーとして配置されましたが、職務等級に変更はなく、基本給及び特別営業手当は減額されることはなかったものでありませんでした。そのため、本件措置が均等法9条3項又は育介法10条が禁止する不利益な取扱いに該当するかが争点となり、原審判決と本判決では、この点で判断が分かれていました。
- 本件において、Xは、出産前は37人の部下を擁するチームリーダーとして業務に従事しており、①チームのターゲット達成に向けた部下のマネジメント(部下のターゲットの進捗状況や営業方法の確認、部下に対する教育及び指導、営業場所の割り振り、シフトの作成、経費の管理、予算の設定等)、②担当営業場所との関係性を強化するための活動(当該営業場所における生産性の高い販売の仕組みの構築等)、③新たな場所での販路の開拓、④チームリーダー会議や本社役員との会議への参加等など、管理職として幅広い業務を行っていました。そして、Xはチームリーダーとして業績を上げ、多額のコミッションやインセンティブが支給されていました。また、Xは、チームリーダー昇格前のセールスエグゼクティブ時代にも既に平均して6人の部下を持ち、その実績を評価され、当時の副社長からは女性管理職のロールモデルと言われてチームリーダーまで昇進したものであり、これからの自らのキャリアに対する期待を抱いていました。
しかし、復職した平成28年8月に控訴人が任じられたアカウントマネージャーの業務内容は、一人の部下も付けられず、目標としての契約件数、獲得枚数、売上目標等が示されることもないまま、新規販路の開拓に関する業務を行うこととされ、同年10月からは700件の電話リストを与えられ、優先して取り組むように指示されて同リストを使った電話営業を行うというものでした。
そのため、裁判所は、均等法及び育介法の趣旨及び目的を踏まえ、基本給や手当等の面において直ちに経済的な不利益を伴わない配置の変更であっても、業務の内容面において質が著しく低下し、将来のキャリア形成に影響を及ぼしかねないものについては、Xの業務内容の変化に着目し、一人の部下も付けずに電話営業を主体とする新規販路の開拓業務を担当させたという点において、当該配置転換が不利益な取扱いに当たると判断しました。
その際、上記最判の判断枠組みを参照し、Xの自由な意思に基づいて当該配置転換を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか(上記①)、当該措置につき均等法9条3項又は育介法10条の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するか(上記②)についても検討しています。本件においては、いずれも認められないとしています。
5. 本判決からみる会社の対応策
本件のように、会社が従業員の出産や育児休業を理由に、当該従業員を業務量の少ないポジションに配置転換した場合、転換後のポジションが転換前と基本給や手当等が変わらなかったとしても、均等法9条3項又は育介法10条の不利益取扱いにあたり、違法となる場合があります。
妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後休業又は育児休業の取得を理由に配置転換を行うときは、①従業員が当該転換を承諾しているといえる客観的事情があること、または②当該転換措置を取らずに従業員を復帰させることに業務上支障があり、会社において当該措置を採る必要性と従業員が受ける不利益に照らして、均等法や育介法の趣旨・目的に反しないことが必要です。
そのため、配置転換を行う前に、当該従業員がどんな働き方やキャリアを望んでいるかを確認し、当該配置転換を行う業務上の必要性などをしっかりと説明しなければなりません。
しかし、従業員の承諾を客観的事実から認められるためには、どのようなことが必要か、承諾を得られなかったとしても、当該配置転換が法の趣旨に反しないか否かについては、法律知識が必要です。
そのため、従業員のトラブルを予防するためにも、従業員の出産・育休から復帰後の対応についてお困りの際には、是非弁護士にご相談ください。