

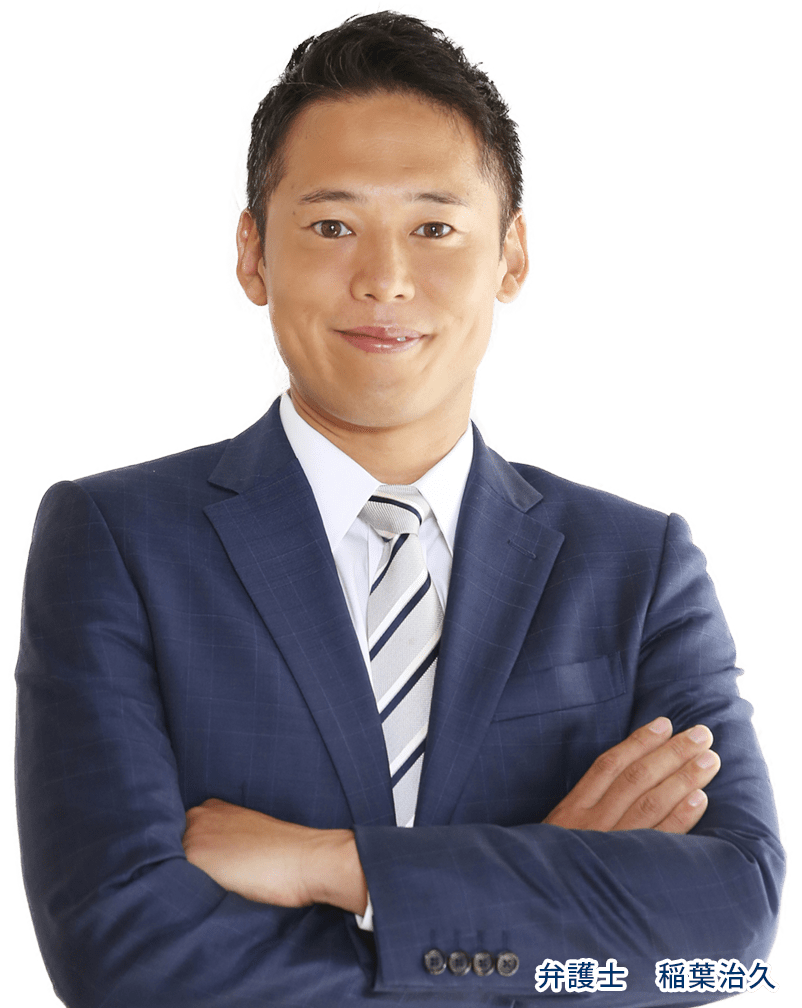
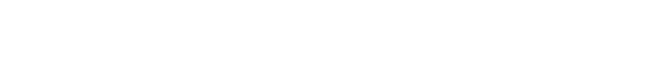
- 離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れない
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
- 財産分与の金額に納得できない
- 突然、相手が家を出て行った
- 離婚を考えているが、どのように話を切り出してよいか分からない
- 子供の親権や養育費がどうなるのか心配
- 離婚をしても今の家に住み続けたい
- 相手のモラハラに耐えられない

1離婚とお金

- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割
- 公的扶助
2離婚と子供

- 親権
- 監護権
- 面会交流
3手続きの流れ

- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
4戸籍と姓

- 親の戸籍に戻る
- 戸籍を作る
- 婚氏続称制度
1離婚とお金 “大切なお金の問題で後悔しないために”
離婚にともない慰謝料が認められるケースとは




慰謝料はどれくらい請求できるか
慰謝料の額には明確な基準はありません。 金額については、離婚に至った経緯、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度や回数等によって決まってきます。一般的には300万円程度が平均的ですがそれぞれの家庭の事情、離婚に至る経緯などによって、金額は異なりますので、まずはご相談下さい。財産分与の種類
大きく分けて3つの種類があります。清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算扶養的財産分与
離婚により困窮する(元)配偶者の扶養慰謝料的財産分与
傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
取り決めの時期
養育費は、子どもに必要がある限り、何時でも請求できますが、離婚時に「要らない」などと言ってしまった場合などは、その後の請求の時には、取り決めが難航することもあります。 養育費の請求権は、子どものためのものです。子どもと別れて暮らす親との関係を大事にするためにも、 離婚時にきちんと取り決めましょう。取り決めの方法
取り決めの方法としては、 ①話合いで決める ②家庭裁判所の調停や審判、裁判で決める などの方法があります。①の話し合いでお互い納得して決めるのがベストな方法ですが、取り決めたことは、口約束だけでなく、書面にしましょう。 費用や手間はかかりますが、公証役場で、公正証書にするのが一番です。公正証書を作成しておくと、万一、不払いになっても強制執行(相手の給料等から差し押さえ)が可能です。 尚、話合いでまとまらなければ、②の家庭裁判所の調停や審判、裁判で養育費を決めます。 家庭裁判所の調停や審判、裁判で決まれば執行力のある債務名義と同じような効果があるので、支払がない等、いざというときには、強制執行(差押え)も可能となります。どんな年金でも分割可能か
この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。また、「婚姻前の期間」の分も反映されません。さらに、将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえるという制度ではなくあくまでも保険料の納付実績の分割を受けるという制度となります。2離婚と子供 “お子様の将来は決まっていますか?”
親権
監護権
面会交流
3手続きの流れ “離婚の手続きについて知っていますか?”
協議離婚

離婚する人の全体の約90%がこの協議離婚により離婚しています。 当事者が同士で直接話し合い、離婚意志をもって合意することが原則です。
調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の調停において、夫婦間の婚姻関係を解消、離婚の合意が成立し、調書に記載したときに、離婚と同様の効力を持ちます。離婚調停後、10日以内に離婚の届け出を出す必要があります。
裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合、裁判をして離婚や慰謝料等を請求することとなります。 裁判離婚をするには、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。また、裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。
4戸籍と姓 “新たな生活には準備が必要です。”
旧姓に戻し、 親の戸籍に戻る
旧姓に戻し、 新しく戸籍を作る
姓を継続し、 新しく戸籍を作る
稲葉セントラル法律事務所の解決事例
相談者:30代 女性
相談内容
夫との性格の不一致で別居を開始し、別居後3年が経過してしまいましたが、親権や財産分与で話し合いがまとまらず、離婚に至っていませんでした。子どもの親権と養育費はどうしてもほしいが養育費の金額としていくらが適正なのかわからない、財産分与も要求したいが、財産をすべて夫が管理していたため財産内容が不明な為、どうしたらいいのかご相談に来られました。
相談後
養育費の算定については、夫の収入をいくらとみるか、収入の資料を分析し、適正な金額をアドバイスをすることができました。また、財産分与についても、まずは、手掛かりとなる財産の資料をできるだけ探してきてもらい、そこから推測し、相手方に財産資料の開示を求めることで、財産分与の請求を行うことができました。 調停での話し合いの結果、相談者が親権を取得することができ、また、二人の子の養育費として月額10万円を獲得、不払いの場合の強制執行の実効性を担保するとともに、今後進学する際には別途協議を行う旨の調停条項を調整しました。
相談者:60代 女性
相談内容
長年連れ添った夫に突然離婚を切り出されました。夫婦関係は以前から冷め切っていた為、離婚には同意するつもりですが、老後のお金の不安があるので、きちんと財産分与や年金分割について調停で取り決めてから別れたい。でもお金の管理はすべて夫が一人で行っていたため、財産について把握できていない部分があるのでどうしたらいいか。
相談後
財産分与については、まずは、手掛かりとなる財産の資料をできるだけ探してきてもらい、そこから推測し、相手方に財産資料の開示を求めることで、財産分与の請求を行うことができました。 その結果、納得のいく財産分与・年金分割が決定し、老後の見通しも明るくなりました。
相談者:20代 女性
相談内容
夫が浮気していると感じたので、探偵に調査を依頼したところ、夫は女性と不倫関係にあることがわかりました。 相手の女性に慰謝料を請求しようと考えましたが、実際に、その女性と顔を合わせたりして自ら交渉することに対し、とても抵抗があった為、弁護士へ依頼しました。
相談後
依頼を受けて、まずは、相手の女性に対して内容証明郵便にて、慰謝料の請求をしましたが何も応答がありませんでした。 次の段階として、訴訟をすすめていった結果、相手の女性は、訴訟まで起こされるとは考えていなかったようで、少しでも早く解決させたい様子でした。その結果、早い段階で、慰謝料を支払うことを認め、訴訟上の和解が成立し、相手の女性から支払いを受けることが出来ました。







