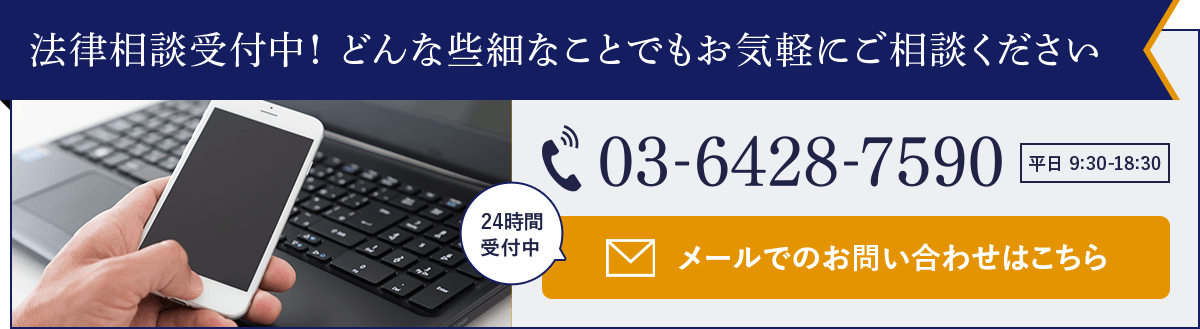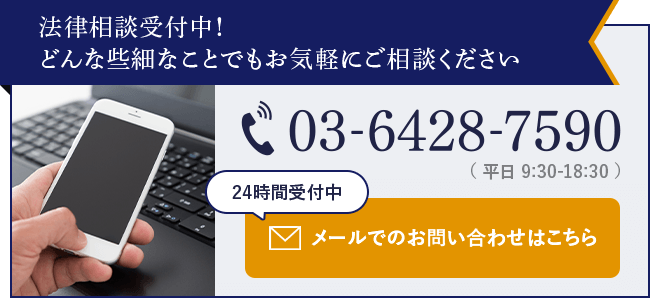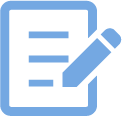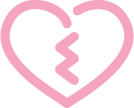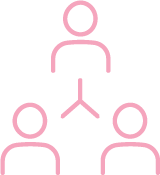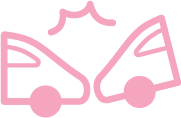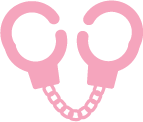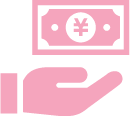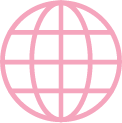どんなときに相続放棄をするべきか
1.はじめに
司法統計年報によると、令和5年度の盛岡家庭裁判所における相続放棄の申述の受理数は、3,610件¹でした。令和4年度は約2,900件、令和3年度は約2,800件と、岩手県内での相続放棄の件数は増加傾向にあります。
相続が発生した際の選択肢は複数ありますが、相続放棄はどのような場合に行うべきなのでしょうか?
本記事では、相続放棄の意義や、単純承認、相続放棄、限定承認の違い、どのような場合に相続放棄を行った方がよいのかなどを解説します。
2.相続の際の選択肢は3つあります
相続は、被相続人が亡くなられると発生します(民法(以下法令名省略)882条)。相続が発生すると、原則として、相続人は被相続人の預貯金や土地の所有権、借金などの権利義務の一切を承継することとなります(896条)。
そのため、被相続人が借金をしている場合などに相続をされる方の中には、借金等の負担から逃れたいと考えられる方もいらっしゃると思います。そこで、相続においては、3つの種類の方法の中から希望する方法を選んで相続するか否かなどを決めることができます。
単純承認
単純承認は、プラスの財産マイナスの財産を含む全ての権利義務を引き継ぐ方法です(920条)。
相続の際に特に何も手続しなければ、自動的に単純承認したことになります。
3つの相続の方法の中で、一番基本的な相続方法です。
相続放棄
相続人の権利義務を一切相続しない制度が「相続放棄」です(938条)。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったことになります(939条)。
つまり、被相続人の預貯金や不動産などの積極財産や、借金やローンなどの消極財産を含むすべての財産を受け継がなくなります。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、単独ですることができます。
なお、相続放棄をする場合には、期間制限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」(915条1項本文)に、家庭裁判所に必要な書類を提出するなどの手続きを行う必要があります。
限定承認
限定承認は、相続人が、被相続人の債務について、相続財産の中の積極財産(プラス財産)の限度で責任を負うという制度です。
相続人は本来相続債務の全てについて責任を負うことになります(無限責任)が、過大となる債務の承継から相続人の利益を守るために、相続財産を限度とする有限責任に転化する手段として創設されました。
限定承認は、プラス財産の総額を上限としてマイナス財産の弁済を行います。つまり、マイナス財産の方がプラス財産よりも多い場合であっても、相続人はプラス財産で弁済しきれないマイナス財産については弁済の責任を負わないことになります。
そのため、相続財産調査で判明していなかった債務について、あとから請求された場合でも、プラス財産の範囲内で清算することができます。また、プラス財産の方がマイナス財産よりも多い場合は、マイナス財産を弁済した後で残余財産を受け取ることができます。
限定承認の手続きは、相続放棄と同様に、相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があるという期間の制限があります(915条1項)。
もっとも、相続放棄は相続人一人でもおこなうことができますが、限定承認は、共同相続人の全員で行う必要があります(923条)。そのため、すでに単純承認や相続放棄をしている相続人がいれば、その時点で限定承認を選択することはできなくなってしまいます。
限定承認の手続きは家庭裁判所への申述だけでなく、官報での公告や債権者への清算を行う必要がありますので、限定承認の手続き開始から完了するまでに1年以上かかることも少なくありません。
3.相続放棄はどんなときにすべき?
⑴ 相続財産に負債が多い場合
被相続人の財産ついて、プラスの財産とマイナスの財産を比べた結果、マイナスの財産が多いという場合は、相続放棄をすることで相続により負債を負うことを回避できます。
たとえば、被相続人が多額の借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済しきれないケースでは、相続人がそのまま相続することにより、借金を相続人が返済しなければならなくなります。
そのため、このようなケースでは、相続放棄について検討することが考えられます。
⑵ 相続問題に巻き込まれたくない場合
上記のとおり、相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったことになります(939条)。
相続人としての地位が無ければ、遺産分割協議や調停などに参加する必要が無くなるため、相続に関する紛争に巻き込まれるのを回避することができます。
⑶ 被相続人の財産を特定の相続人に全て承継させたい場合
特定の人に遺産を集中させたい状況であれば、他の相続人が全員相続放棄する方法が有効であると考えられます。
相続放棄をした人は相続人ではなかったことになりますので、他の相続人が取得する相続分を増やしたり、相続人でなかった者を相続人とすることができます。
例えば、相続人が被相続人の子2名である場合、そのうちの1人が相続放棄をした場合には、相続人はもう一方の子1名になるため、その者が単独相続することになります。また、相続人が被相続人の子1人で、子が相続放棄した場合には、被相続人の両親などの直系尊属や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(889条1項)。
そのため、「1人に相続財産すべてを承継させたい」、「被相続人の両親や兄弟姉妹に相続させたい」などの特定の者に相続をさせたいといった場合にも、相続放棄をすることが考えられます。
特に資産と負債の両方を特定の相続人に集中させる場合、他の相続人が全員相続放棄する方法が考えられます。
4.相続放棄をするにあたっての注意点
⑴ 単純承認とみなされる場合がある
上記のように、単純承認とは、相続人が被相続人の財産(プラス財産とマイナス財産)すべてを相続するという、一般的な方法です。期間内に限定承認または相続放棄を行わなかった場合に、自動的に単純承認したことになります(921条2号)。
この場合だけでなく、相続人が相続財産の全てまたは一部を処分した場合にも、単純承認したとみなされます(同条1号)。
処分行為については、たとえば、不動産を売却や贈与、名義の書き換えや、物を破損させる行為がこれにあたります。
また、相続放棄を行った後でも、相続財産の全部または一部の隠匿や私用での消費をおこなった場合や、悪意で相続財産に記載しなかった場合には、相続放棄をした後でも、単純承認したとみなされてしまう(同条3項本文)ので、注意が必要です。
⑵ 相続放棄を撤回することができない
相続放棄の申述が受理される前であれば、申述の受理申立を取り下げることができます(家事事件手続法82条1項)。
しかし、相続放棄ができる期間であっても、撤回(相続放棄の申述が受理された後で、後から相続放棄の効力をなくすこと)をすることができません(919条1項)。
5.弁護士にご相談ください
これまでみてきたように、相続放棄を行うことで、被相続人が残した債務を引き継がないということができますが、他方でプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。相続財産に債務があるため相続放棄をしたが、実は預貯金や土地などが多数あり、総合的に見てプラスだったことが判明した場合でも、相続放棄を撤回することはできません。
そのため、相続放棄にあたっては、被相続人の財産の調査を行ったうえで判断すべき場合があります。
また、相続放棄をおこなうと、後順位の相続人に相続の権利が移転します。そのため、自分が相続放棄を行った場合、次にだれが相続人になるのかも併せて調査する必要がある場合があります。
弁護士にご相談いただければ、相続人や相続財産の調査を行ったうえで、相続放棄をすべきかどうかをアドバイスさせていただきます。また、相続放棄を行う場合には、弁護士が手続きを代理し、家庭裁判所への申述や債権者への対応も行うことができます。
相続放棄ができる期間は限られていますので、相続が発生した場合には、お早めに弁護士にご相談下さい。